【電気代高騰の背景】
2025.07.14
皆さん、こんにちは!
新潟での太陽光・系統用蓄電池のことならテクノナガイソラーレにお任せ!
法人営業部の酒井です。
さて今回は『電気代高騰の背景』について書いていきます。
ぜひ皆様の参考になればと思いますので、最後までお読みくださいね!
==========目次===========

1.国内の電力供給不足
2.燃料価格の高騰
3.まとめ
1.国内の電力供給不足
電気代高騰の理由のひとつに、国内の電力供給不足が挙げられます。
東日本大震災以降、原子力発電所が停止されたことにより国内の電力供給容量は一次的に低下しました。
足りない分をLNGなど輸入化石燃料に頼らざるを得なくなり、それが電気料金の高騰を招いていると言われています。
国内の電力供給不足の要因としてもう一つ上げられるのが、急激な気候変動です。猛暑や寒波の影響で暖房や冷房の使用による電力需要が急激に増えたとき、その需要を賄えるだけの供給電力がないと電力システムが乱れ、大規模停電を起こしてしまいます。
電気はあらかじめ貯めておくことができないため、急な需要に対応することで予想外の出費がかかることがあるのです。
また、近年特に多い雪害や洪水など、電力インフラの機能損壊を招くような気象もまた、電力高騰を引き起こすリスクのひとつです。
家庭生活や産業を維持するための安定した電力供給のためには、電力供給者が様々なリスクを加味したうえで、そのリスクに耐えうるレジリエンス(強靭性)を電力インフラに持たせなくてはなりません。
気候変動が予測不可能になればなるほど、電力インフラが抱えるリスクが増え、対策コストもかさむことになるのです。
2.燃料価格の高騰
日本は電力の多くを火力発電によって賄っています。原料は主に石油(36.3%)・石炭(25.4%)・LNG(21.5%)を使用しており、これらの原料の価格高騰が電気代高騰に大きく影響しています。
燃料価格高騰の背景には、新型コロナウイルスからの経済回復の影響やロシアによるウクライナ侵略、世界的なインフレや円安などがあり、いずれも不透明な世界情勢が原料の高騰を引き起こしているものと考えられています。
さらに、価格高騰にはこのような情勢不安だけでなく、近隣諸国の需要も関係しています。
近隣諸国の影響で価格が高騰した最も顕著な例は石炭です。石炭は化石燃料の中でも比較的安価で供給が安定している原料ですが、その石炭はこの10年で最も高い水準に価格が急騰しました。
主な理由に、中国における需要のひっ迫が挙げられます。中国は世界一の石炭消費国であり、同じく石炭を必要とする我が国の石炭輸入価格や供給量に大きな影響を及ぼす存在であることから今後もその動向が注目されます。
政府は、急激な電気料金の高騰から国民生活を守るため、さまざまな対策を用意する姿勢です。ですが、世界情勢がまだまだ不透明であることなどから、この先も明るい見通しは期待できません。
また、日本のエネルギー自給率は先進国の中でも11.3%(2020年)と低い水準にとどまっており、安全で安定した電力供給へ向けてさらなる調整や取り組みが必要です。脱炭素を推し進める世界的流れの中で、日本の化石燃料に依存する姿勢は逆行しているように見えるかもしれません。
しかし、安定した電力供給、経済性、安全性などから考えてみると、火力発電は引き続き重要な電源と考えられています。
政府は、環境負荷の少ないクリーンな火力発電の開発を進めながら、同時に再生可能エネルギーへの電源置換を進めています。
太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの導入は、地球環境負荷を低減するための施策という点ではもちろんですが、より身近な電力コスト低減への動きによって現実味を帯びています。
3.まとめ
いかがでしたでしょうか?
本日は『電気代高騰の背景』について書いてきました。
化石燃料由来の電気料金が高騰を続ける中、再生可能エネルギー設備の導入や省エネのための設備更新は喫緊の課題です。
補助金の活用など、あらゆる手段を検討しながら対策を進めていきましょう。弊社の知識や経験から、その過程をサポートさせていただくことができましたら幸いです。
下記フォームより、お問い合わせをお待ちしております!











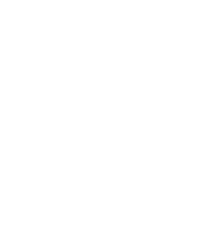 会社案内
会社案内