【電気工事におけるコア抜き作業とは?】
2025.09.11
工事部の鈴木です。
今回は、電気工事の現場でよく耳にする「コア抜き」という言葉について解説致します。
言葉の意味は、コンクリートやモルタルなどの構造物に、円形の穴を開ける作業を指します。
建物の電気配線や配管をスムーズに通すために欠かせない工程であり、専門的な技術と正確な施工が求められます。
この記事では、電気工事におけるコア抜きの基本的な説明から、作業手順、注意点、費用目安までを詳しく解説します。
【コア抜きとは】
コア抜きは、コアドリルという専用機械を使い、コンクリートを円筒状にくり抜く作業です。
穴を開けた後に取り除かれる円柱状のコンクリート片を「コア」と呼ぶことから、この名称がついています。
電気工事では以下のような場面でコア抜きが必要になります。
|
|
|
|
・電線管やケーブルの貫通→ |
・幹線ケーブルや分岐配線の経路確保 |
|
・弱電工事→ |
・LANケーブル、防犯カメラ、インターホンなど |
|
・空調・換気設備→ |
・エアコンの冷媒管、換気ダクトの通路 |
|
・コンクリート品質検査→ |
・コアを抜き取り、強度試験を行う |
このように、コア抜きは電気工事に限らず建築や設備工事でも広く行われる重要な工程です。
【コア抜きの作業手順】
電気工事でのコア抜きは、単に穴を開けるだけではなく、建物の安全性を確保しながら正確に行うことが求められます。ここでは、一般的な作業手順を順を追って説明します。
- 事前確認(計画)
まずは図面を確認し、穴を開ける位置を決定します。
特に次の点を確認することが重要です。
①耐力壁や梁など、構造上重要な部分でないか
②貫通部が防火区画に該当しないか
③穴径や深さが適切か
④施工後に防火処理、防水処理が可能か
構造上重要な箇所に無断で穴を開けると、建物の耐震性能に悪影響を与える可能性があるため、必ず施工管理者や設計者と事前に打ち合わせを行います。
- 鉄筋探査
コンクリート内部には鉄筋や配管が埋め込まれている場合が多くあります。
これらを誤って切断しないように、鉄筋探査機を使って内部状況を確認します。
鉄筋を傷つけてしまうと、建物の強度が低下するだけでなく補修にも多大なコストがかかります。
探査はコア抜き作業の前に必ず行うべき工程です。

- コアドリルの設置
コア抜きには専用のコアドリルを使用します。
正確な位置で穴を開けるために、アンカーベースを床や壁にしっかりと固定し、機械がぶれないように設置します。
コアビット(刃先)は穴径に合わせて交換可能で、電気工事では直径30~150mm程度のサイズがよく使われます。
- 穴あけ作業(湿式・乾式)
穴あけ作業には湿式工法と乾式工法があります。
|
湿式工法→ |
冷却水を使い、粉じんが少ない。刃の寿命が長い。 |
(屋外、集合住宅、工場など) |
|
乾式工法→ |
水を使わず、汚泥処理不要。粉じんが発生する。 |
(室内や水を使用できない現場) |
湿式の場合は、コンクリートを削る際に発生する熱を水で冷却し、粉じんを抑えます。
乾式は水を使わないため後処理が簡単ですが、粉じんが多く発生するため、集塵機を併用するなどの対策が必要です。

- 後処理(仕上げ)
穴あけ後は次の仕上げ作業を行います。
- 穴の周囲にできたバリ(コンクリート片)の除去
- 防水処理(屋外や水回り)
- 防火区画の貫通部処理(耐火パテ、ケイカル板など)
- ケーブルや配管を挿入後、隙間をシーリング材で密閉
特に防火処理は建築基準法第112条により義務付けられており、消防検査でも重点的に確認されます。
【コア抜き作業の注意点】
コア抜きは単純に穴を開けるだけの作業ではなく、建物の安全性や施工品質に関わる重要な工程です。以下の点に注意しましょう。

- 構造体への影響を最小限にする
- 耐力壁や梁へのコア抜きは極力避ける
- 鉄筋は原則切断しない
- やむを得ない場合は構造設計者に相談
- 安全対策を徹底する
- 粉じん対策(マスク、集塵機)
- 作業中の落下物防止(床下に養生)
- 騒音対策(防音カバーや作業時間の調整)
- 電動工具使用時は感電防止のため漏電ブレーカを設置
- 防火区画・防水区画の処理
- 防火区画貫通部は耐火パテや耐火スリーブを使用
- 屋外や水回りは防水処理を確実に行う
- 消防検査や建築検査で指摘されやすいポイントなので要注意
【まとめ】
コア抜きは電気工事において欠かせない工程であり、建物の安全性や機能性に直結します。
ポイントは以下の通りです。
①コア抜きは配管やケーブルを通すために行う穴あけ作業
②作業前には図面確認と鉄筋探査が必須
③穴あけ後は防火・防水処理を確実に行う
④建物の構造を損なわないよう慎重に施工する
⑤専門業者への依頼で安全性と品質を確保する
コア抜きを適切に行うことで、施工後のトラブル防止や建物の耐久性向上にもつながります。
電気工事に携わる方は、計画段階から慎重に準備を進め、確実な施工を心がけましょう。




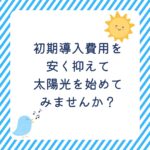






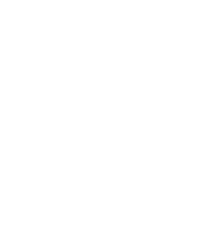 会社案内
会社案内